トピックス
法はなぜ必要なのか──綱島教授が語る「社会を支える法の役割」
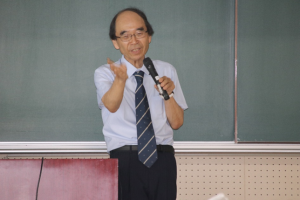 今回は総合政策学部法律学科法律コース1年生の綱島公彦教授の授業「法律コースの魅力とその意義」におじゃましました。
今回は総合政策学部法律学科法律コース1年生の綱島公彦教授の授業「法律コースの魅力とその意義」におじゃましました。
講義は「法律は何のためにあるのか?」という問いから始まりました。「法律」と聞くと、社会のルールであり守らされるものと捉えがちですが、実際には「個人の尊厳」や「基本的人権」を守るために存在しており、現代社会における多様な国家の権力を制限することで、私たち一人ひとりの人権を保障する手段であることが示されました。
また、法律が自動的に個人を守ってくれるわけではなく、自分自身の尊厳や権利を守るには、どのように法律が機能しているかを理解する必要があることを指摘。その上で私たちは他者と共に社会を構成している中で、ときに「自分の尊厳」と「他者の尊厳」が衝突(紛争)する場面もあります。そうした対立を公正に調整する手段として法律の役割を捉え、「自分を守り、同時に他者も守る力」を身につけることこそが、法律を学ぶ本質的な意義であると語られました。
その一例として、「法律の解釈」が庶民の暮らしに及ぼす影響を示す例としてサラ金などの「消費者金融問題」が取り上げられました。
昭和40年代から平成にかけて、「利息制限法」をめぐり、金融業者と裁判所の間で解釈を争う動きが続きました。当時は法定上限を超える40%近い高金利での貸し付けも見られましたが、司法判断の積み重ねにより過払い利息の返還まで進み、超高金利の業者は姿を消していきました。
講義を受けた学生からは、「法律が自分や周囲の人を守る手段であることを実感しました」「これまで法律は自分とは無縁のものと感じていましたが、学ぶ意義を感じ、関心が湧きました」といった声が寄せられ、法律への興味を深める機会となりました。
