音楽が拓いた英語力―英検1級合格への道
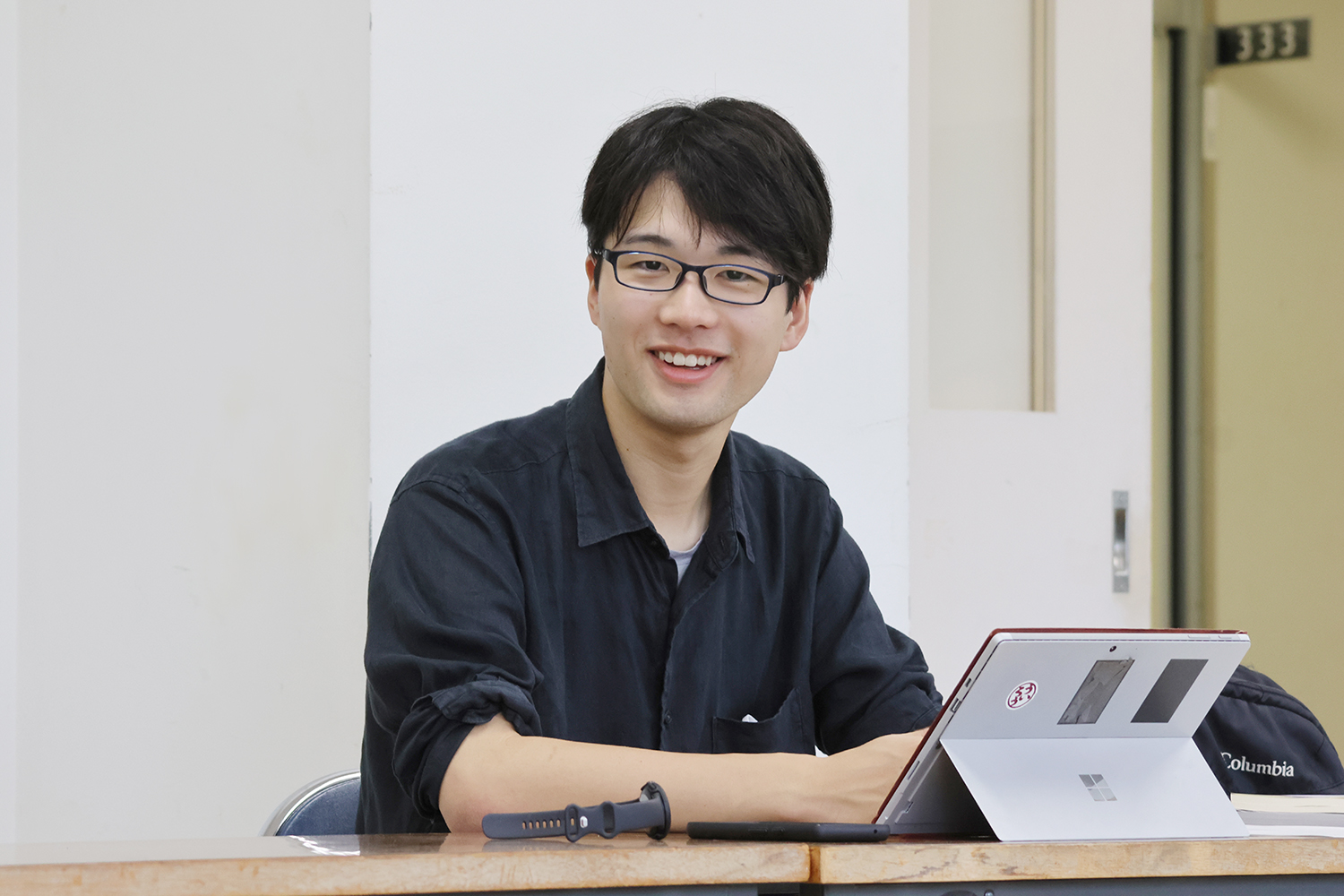 法学部国際学科4年 佐藤誠剛さん(ノースアジア大学明桜高等学校出身)
法学部国際学科4年 佐藤誠剛さん(ノースアジア大学明桜高等学校出身)
英検1級 秋田銀行
英語力を育てた音楽理論
2歳でエレクトーンを始めたことが音楽との最初の出会いでした。中学・高校では吹奏楽部でクラリネットを担当し、高校2年からはポップスを演奏するためにピアノを任されるようになりました。
この頃から音楽理論への探求心が芽生え、即興演奏に必要なスケールやコード進行、楽曲分析を学びました。こうして磨いた分析力がやがて英語学習へと繋がり、私の世界をさらに広げることになったのです。
地政学が開いた英語学習の扉
大学入学時、私の英語力は英検3級レベルでした。実は英語に特別な興味はなく、地政学への関心から大学を志望しました。安全保障論ゼミで、国際紛争の原因や各国の安全保障政策などを研究したいと考えていました。
ところが、大学の英語授業は高校までの「勉強」とは全く異なり、新鮮な体験に溢れていました。カナダ人の先生との個別レッスン、海外の人とのオンラインフリートークなど、英語を「楽しむ」ことを学びました。
とりわけ印象的だったのは、映画を教材にした授業です。登場人物のセリフ分析や文化的背景を探ることで、英語を単なる知識としてではなく、コミュニケーションの道具として身につけることができました。

映画を教材にした授業で「生きた英語」を体感し、英語学習が楽しくなったと目を輝かせる。
教えることで深まる知識 —英検1級への挑戦—
大学1年で英検2級、2年で準1級を取得しました。その経験を生かし、塾講師のアルバイトを始めたことが、英語力向上への転機となりました。
大学受験の英語長文を指導する中で、読解力は大きく向上しました。
「もっと英語力を伸ばしたい。自分の世界を広げたい。」
そう思うようになってからは英検1級合格を目標に定め、本格的な勉強を始めました。しかし、一度目の挑戦は不合格。語彙力の足りなさを痛感しました。

英語力を高める上で、5文型を知ることが効果的な学習方法であることを強調する。
英検1級への本格的な挑戦—壁を乗り越えた三度目の試験—
一度目の受験後、語彙力不足を克服するため単語帳アプリを使い、毎日50個の新しい単語学習と250個の復習を徹底的に行いました。これらの練習を1日も欠かさずにしても、まだ足りません。結局二度目も不合格。リスニングが課題となりました。そこで、YouTubeの地域設定をUKに変更し、字幕なしで映画やゲームを視聴することで耳を鍛えました。
三度目の挑戦に向けては、過去問や問題集を徹底分析し、AIによる英作文添削も活用しました。そして三度目の挑戦でついに悲願の英検1級合格を果たしました。
音楽を通して培われた分析力が導いた英語力
振り返ると、音楽理論の「テンションノート」分析は、英語の語彙分析と驚くほど似ていると感じます。コード(和音)は、ド、ミ、ソ、シのように音を重ねたものを指し、テンションノートとは、それに音を加え、響きに彩りや奥行きを与えるものです。
この「響き」を探る作業は、英単語の語源分析と共通します。「prodigious」なら、「pro-」(前へ)と「-digious」(示す)から、「並外れた」という意味を推測できます。
一見すると異なる分野に見えますが、コードの構成要素を解き明かし、響きを考慮するプロセスは、英単語を分解して意味を探る作業と共通しています。音楽を通して培った分析力が、英語学習を楽しむための力となり、自分の世界を広げてくれました。

大学祭の吹奏楽ポップスステージでは編曲を担当。楽曲の構成を分析し、楽器の特性に合わせてアレンジを加える作業を通して、英語学習との共通点を見出したと語る。
後輩へのメッセージ
私は決して最初から英語が得意だったわけではありません。しかし、地道な努力と継続によって英検1級合格を達成することができました。また、異なる分野の学びが思わぬところで繋がることがあります。だからこそ、大学生の皆さんには様々なことに興味を持ち、失敗を恐れずに積極的に挑戦してほしいと思います。
私はこの春から地域の銀行に就職します。「Think Globally, Act Locally」という座右の銘を胸に、地域経済の発展に貢献できる銀行員を目指します。
皆さんも大学での活動を通して、自分の興味や関心を深め、世界に目を向けてください。そして、そこで得た知識や経験を地域社会に還元できるような人になってほしいと願っています。
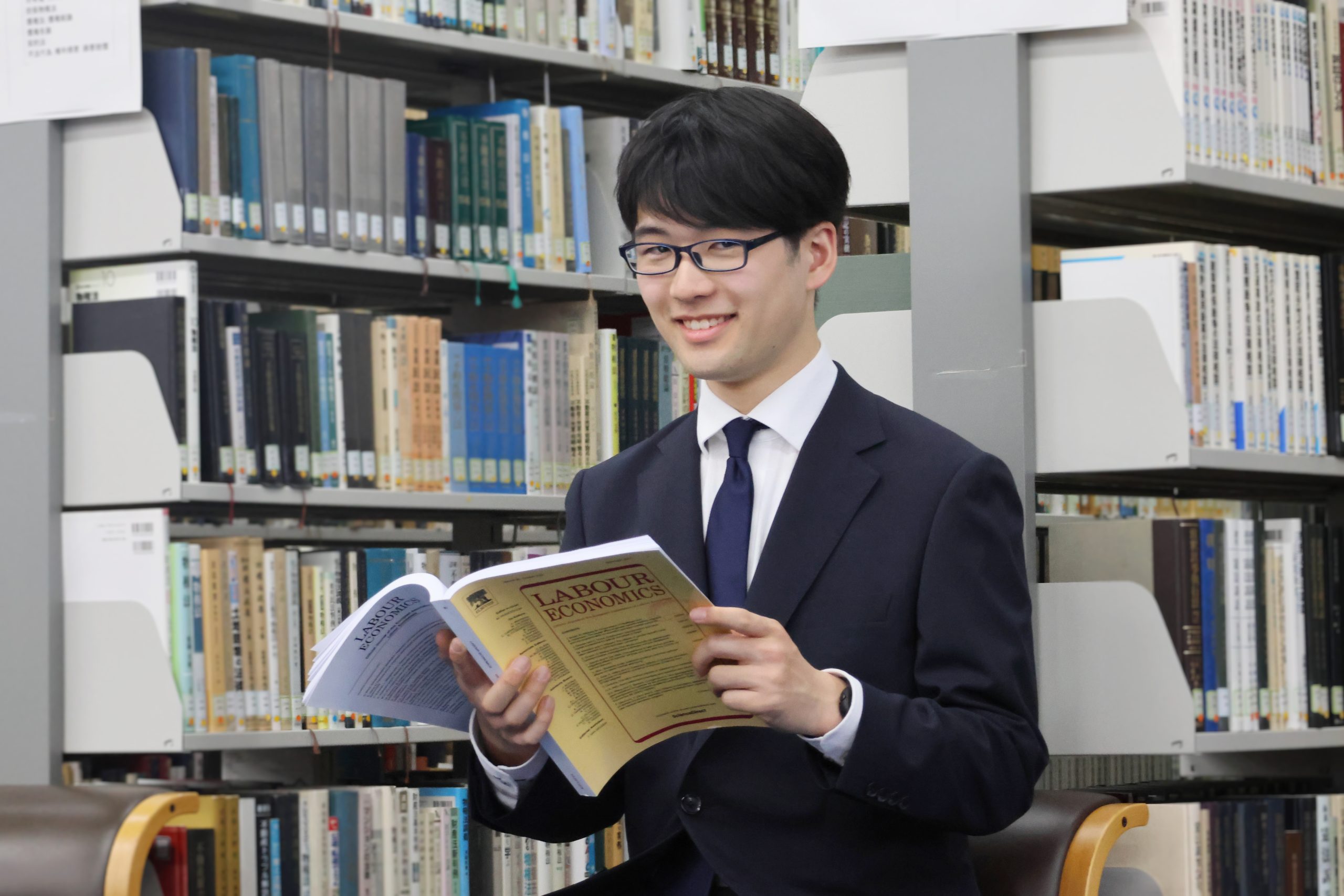
英検1級取得してもなお、日々の研鑽を怠らず、英語力向上に努めている。

